新型コロナウイルス感染症が蔓延することになり身の回りの日用品などの消毒に対処する必要がでてきました。
とくに車いす生活を送る立場としては消毒は気になる問題です。
なぜならいくら手をキレイに洗っても車いすを漕ぐため車輪に付くハンドリムと呼ばれる場所が汚れていると意味がないからです。
この意味は自宅のドアノブやリモコンなど手が触れる場所すべてに当てはまります。
いささか神経質ではありますが病的なレベルでなければ身の回りをキレイにして損はありません。
そこで車いすの車輪、フレームや自宅での消毒に利用するため次亜塩素酸の素で除菌水を作ることを考えました。
次亜塩素酸の素を活用する利点は任意の濃度で薄めて使うことができるところです。
つまり消毒したい物や対象によって濃度を変えることができるので室内飼いする柴犬の身の回りなどにも活用できます。
車いすなどしっかり消毒しておきたい部分はやや濃度を強めにしたり自由度があります。
今回はそんな次亜塩素酸の素を使った除菌水作りの方法をまとめておきます。
次亜塩素酸の素を使う除菌水作りの方法
用意した次亜塩素酸の素は株式会社抗菌美装さんの【ジアテクターP】です。
ジアテクターPは粉末の商品で水と混ぜ合わせて使います。
抗菌美装さんオンラインページではジアテクターPと同じ成分の次亜塩素酸の素を購入できます。
今回はアマゾンプライム加入メリットを活かすためアマゾンから購入しています。
ジアテクターPで次亜塩素酸水を作ってみましたが作業そのものはカンタンでした。
ただ注意したいのはPPM濃度です。
粉末であるジアテクターPを水に混ぜ合わせる工程では計算した分量で用途に適したPPM濃度で除菌水を作ります。
用途に応じた除菌水を使い分けるためにベース液を作る手順から説明します。
つまりベース液を用意⇒用途に応じてベース液を薄めた除菌水を作る。
このような使い方を想定します。
ジアテクターPでまず次亜塩素酸ベース液を作る
ではジアテクターPから次亜塩素酸ベース液の作り方を説明します。
今回のベース液濃度は1000PPMを狙いました。
つぎに用意した容器と器具です。

- ジアテクターP
- ドリップサーバー
- 電子はかり
- 漏斗(じょうご)
- 容器(酒瓶720ml)
- 水道水
1000PPM濃度のベース用希釈液を作る方法は?
ジアテクターPの商品説明には1000PPM濃度の希釈液を作るにあたって1ℓの水に対してジアテクターPを1.67gとなっています。
PPMは100万分の1で表している単位です。
PPMの理解ついてはちょっとややこしくアタマが痛い内容ですが必死にがんばって別記事でまとめました。
参考にしてください。
【関連記事】次亜塩素酸水とPPM単位について
▼ベース液を保管する容器についてご注意
最初はペットボトルの容器で作ろうかと考えました。
しかしペットボトルだと透明なので日光や照明の影響で劣化が進みます。
ですから遮光性のある色つきの酒瓶を使うことにしました。
ペットボトルだと長期利用に対応できないので酒瓶にして正解だと思ってます。
1000PPMの希釈液を500ml作った
ジアテクターPの説明には1ℓの希釈液の作り方が記載されています。
今回は720mlのガラス瓶を使うことになったので500mlの分量でベース液を用意することにしました。
つまりジアテクターPの粉末は1.67gの半分の0.8gを水道水に加えることになります。
実際の手順
用意したコーヒーサーバーに500mlより少し足りないぐらいの水を入れました。
量りの上にサーバーを乗せてコップに入れた水を少しづつ加えながら500mlちょうどにしました。
酒瓶にジアテクターPの粉末を入れたあと漏斗を瓶に乗せ水道水を流し込むだけです。
粉末は混ざりにくいのでしっかり容器を振って粉末を溶かします。

数十秒くらい瓶を振れば全て溶けることを確認できます。
今回は500mlで作ったので混ぜるのもスムーズでした。
もし2リットルのペットボトルでいきなりジアテクターPの粉末と分量の水を入れてしまうとなかなか混ざりにくいと思います。
少なめの容量でしっかり混ぜたあとに正規の分量の水を足した方が作業性は良いでしょう。
精度の高いデジタルはかりなら計量しやすい
1000PPM濃度の希釈液を500mlで作る場合、計測するジアテクターPの分量は0.83gというシビアな数字です。
自宅で使っていた電子はかりがイマイチ精度が悪く、0.83gを計量しようとしても目盛に反映されません。
結果的に小さじ2杯弱で水に混ぜました。
(ジアテクターPに付属の計量スプーンの両端の片方は分量が0.5gとなっています。)
(もう一方なら大さじ2.0gとなっています。)
正確な条件で次亜塩素酸水を作りたいなら精度の高い電子はかりが必要です。
ただジアテクターPの説明で1Lの希釈液を作る場合、付属のスプーンを使って小さじ3杯と少々との表現もしています。
少々の感覚ならそれほど神経質な計測はしなくても良いイメージです(個人的には)。
キッチリした濃度の次亜塩素酸水を作りたいなら0.01gから計測できるデジタルはかりが欲しいところです。
▼作業上の失敗と注意
次亜塩素酸の計量でデジタルはかりが上手く機能しなかったのでテーブルや床に粉末を少しこぼしてしまいました。
自宅での作業は十分に注意してください。
今回の反省を踏まえると次回は台所のシンクで作業しようと思います。
初めての次亜塩素酸水を作りはこのような内容です。
出来あがった次亜塩素酸水ベース液には作った日付を書いておきましょう。
さてこうして次亜塩素酸水のベース液が出来あがりました。
1000PPM濃度のベース液を薄めて除菌水を使う
作ったベース液は1000ppm濃度ですから使う環境や用途に応じてさらに薄めて活用することができます。
ベース液50mlに水道水を950ml加えれば約50ppm濃度の除菌水としてペット廻りなどに活用できます。
ギターの除菌にも次亜塩素酸水が活用できると個人的には考えています。
しかし金属パーツは錆が発生するとの情報があるので注意も必要です。
ネックの裏側とかを除菌水でクリーニングすれば安心できます。
洗い桶にベース液を100mlと水道水を400ml混ぜれば100PPMの消毒液ができあがりです。
100PPMならクルマの車内などのふき取りに活用できるとのことです。
次亜塩素酸の性質と水溶液成分について
次亜塩素酸は水溶液中で徐々に分解される不安定な物質とされています。
【ウイキペディア】次亜塩素酸について
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A1%E4%BA%9C%E5%A1%A9%E7%B4%A0%E9%85%B8
こうした特徴を持つことから抗菌美装さんのジアテクターPの解説ページでは次亜塩素酸を中性・弱酸性・微酸性のどれにも当てはまると指摘しています。
【関連記事】【抗菌美装株式会社さま】ジアテクターPの性質について
さて自分で作った次亜塩素酸水が実際にどのような水溶液の性質を持つのか確認したくなります。
こうした水溶液の性質を調べる場合の方法にph試験紙を活用できます。
【ph試験紙使い方】
ph試験紙の使い方
ph試験紙で理科実験のようなことを楽しめます。
しかし除菌水として次亜塩素酸水を活用するうえで注意したいのは濃度低下です。
次亜塩素酸水の濃度低下に注意
次亜塩素酸水作ってから日にちが経つごとに濃度が低下していくとされています。
ジアテクターPの製造販売元【抗菌美装】の解説ページでは作った除菌水の保管期限は最短で三か月、最長で六か月とのことです。
さらに濃度は約1か月で半分になると記載されていることに注意が必要です。
つまり出来あがった希釈液は時間が経過することでウイルスへの殺菌効果が弱まっていくと理解できます。
このことから言えるのは作った除菌水は一か月を目安に使い切る、あるいは一度にたくさんの希釈液を用意しないことが得策と言えます。
そんな意味では出来あがった状態の次亜塩素酸水を買い求めるよりも今回使ったジアテクターPのようなパウダータイプは使い勝手が良いのではと思います。
除菌効果が低下していくタイミングで定期的に作り変えて対応できます。
殺菌効果を確認するにはph試験紙などを活用できます。
ph試験紙を除菌水に浸して10前後のph値が出ていれば問題ないです。
まとめ!脊髄損傷の次亜塩素酸水活用メリット
新型コロナウイルスが突如として我々に襲いかかりこれまでの普段の生活がガラリと変わってしまいました。
マスクは不足し転売ヤ-が登場したことを考え、今後消毒アルコールが手に入りにくい状況に備え次亜塩素酸水の活用にたどり着きました。
けれど結果的にこちらの方が使い勝手が良く重宝します。
犬のおもちゃの消毒にも使えるし、アルコールのような手荒れも防ぐことができます。
冬は手にあかぎれができたりするのでアルコール消毒のようにピリピリしみることはありません。
さらにクロスや雑巾を100PPMで作った消毒液に浸して車いすのフレームやハンドリムでふき取ればカンタンに消毒ができます。
アルコールだと容量あたりのコストが高いのでこんな使い方はできません。
日常的に次亜塩素酸を用意する環境ならば除菌水に対応する加湿器の導入もカンタンです。
次亜塩素酸水は脊髄損傷にとってもアナタにとってもコロナウイルスに立ち向かう有用な武器となりえます。
算数が苦手なポンコツにとってPPM濃度の理解はなかなか頭の痛い内容でした。
コロナウイルスと向き合っていくためにも全力でまとめました。
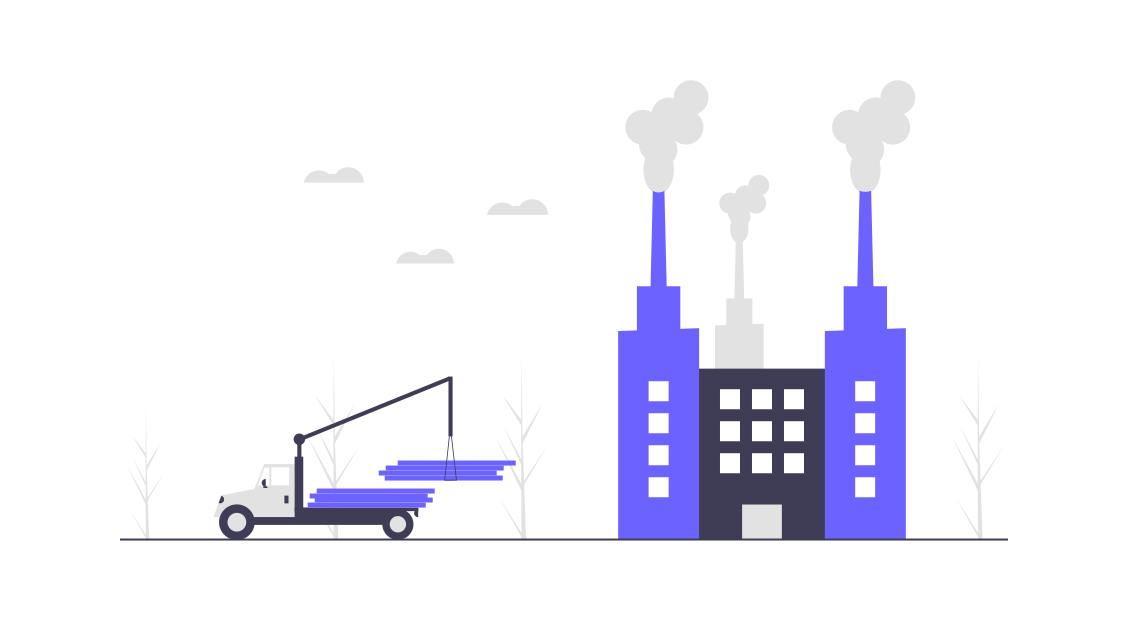










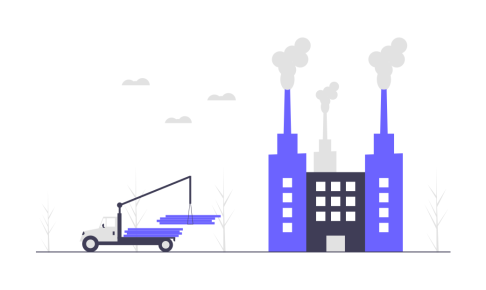














コメントを残す